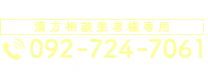漢方コラム
動悸・息切れ

息切れは、日常生活で多くの人が経験する症状です。
階段を上ったり、急いで歩いたりした後に感じる息苦しさは、誰もが経験したことがあるでしょう。しかし、軽い運動でも息切れを感じたり、安静時にも息苦しさを覚えたりする場合は、何らかの健康問題のサインかもしれません。
西洋医学では、息切れの原因として心臓や肺の疾患、貧血、過度の肥満などが挙げられます。一方、東洋の伝統医学である東洋医学では、息切れを体全体のバランスの乱れとして捉え、独自の視点からアプローチします。
この記事では、東洋医学の観点から息切れについて解説し、その対処法や日常生活での工夫について探っていきます。
目次
東洋医学における息切れの捉え方
「気」の概念と呼吸
東洋医学の根幹をなす概念に「気」があります。「気」は生命エネルギーとも言える概念で、体内を巡り、様々な生理機能を支えています。呼吸は「気」を取り入れ、巡らせる重要な働きを担っています。
東洋医学では、呼吸器系の中心である肺は「気」を司る臓器とされ、「宣散(せんさん)」と「粛降(しゅくこう)」という二つの重要な機能を持つとされています。
- 宣散:肺が「気」を体の隅々まで行き渡らせる働き
- 粛降:吸い込んだ空気を下へ降ろし、老廃物を排出する働き
これらの機能が正常に働いていれば、呼吸は滞りなく行われています。
しかし、何らかの原因でこのバランスが崩れると、息切れなどの症状が現れると考えられています。
息切れが起こる原因
東洋医学では、息切れの原因として以下のような病態を考えます:
- 気虚(ききょ):
「気」が足りない状態。疲れやすく、ちょっとした動作でも息切れします。
- 気滞(きたい):
「気」の流れが悪い状態。ストレスや気分の落ち込みで起こりやすく、胸が苦しく感じます。
- 水滞(すいたい):
体に水がたまった状態。むくみや痰が増え、ゼーゼーする息切れが特徴です。
- 陰虚(いんきょ):
体を潤す力が足りない状態。のどが渇いたり、寝汗をかいたりします。
これらの病態は単独で起こることもありますが、複合的に現れることも多いのが特徴です。
息切れをどのように診断するのか?
東洋医学では、患者さんの症状や体質を総合的に判断して治療方針を決定します。この診断プロセスを「四診」と呼び、以下の4つの方法を組み合わせて行います:
- 望診(ぼうしん):
患者さんの顔色、体型、皮膚の状態、舌の状態などを観察します。
- 聞診(ぶんしん):
患者さんの声や呼吸音、咳の様子などを聴きます。
- 問診(もんしん):
症状の詳細、生活習慣、食事の好み、ストレスの有無などを尋ねます。
- 切診(せっしん):
脈診や腹診を行い、体の状態を触って確認します。
特に息切れの診断では、舌診と脈診が重要な役割を果たします。
舌診
舌の状態は体内の状態を反映すると考えられています。
- 舌が白っぽくて歯型がついている:「気」が足りない可能性
- 舌に白い厚い苔がついている:水がたまっている可能性
- 脈が弱くてゆっくり:「気」が足りない可能性
- 脈が滑らかで速い:水がたまっている可能性
脈診
脈の状態も体調を知る重要な手がかりとなります:
- 弱くて遅い脈:気虚の可能性
- 弦脈(げんみゃく、弦を張ったような脈):気滞の可能性
- 沈脈(ちんみゃく、下の方でうっている脈):水滞の可能性
- 浮脈(ふみゃく、力なく上の方でうっている脈):陰虚の可能性
これらの診断結果を総合的に判断し、患者さんの「証(しょう)」を決定します。「証」とは、その人の体質や症状の現れ方を東洋医学的に分類したものです。息切れの症状に対しても、この「証」に基づいて最適な治療方針が立てられます。
息切れに対するセルフケア

薬を飲んで対処療法を行うのではなく、生活習慣の見直しや全体をどう整えるのか?という視点を大切にするのが東洋医学の世界になります。
食事療法
東洋医学では、食事も重要な治療法の一つと考えます。息切れの改善に役立つ食事の工夫として:
- 気虚の改善:
- 消化の良い食事を心がける(お粥、煮込み料理など)
- 温かい食事を摂る
- ニンジン、シイタケ、クコの実などの食材を取り入れる
- 気滞の改善:
- 柑橘類や香辛料を適度に使用する
- 発酵食品(味噌、醤油、酢など)を取り入れる
- 水滞の改善:
- 利尿作用のある食材(ゴボウ、レンコン、冬瓜など)を積極的に摂る
- 塩分や水分の取りすぎに注意する
- 陰虚の改善:
- 潤いのある食材(トマト、キュウリ、ナシなど)を取り入れる
- 刺激物(辛いもの、アルコールなど)を控える
生活習慣の改善
「気」の巡りを良くするためには日々の生活が大切になります。
- 規則正しい生活リズムを保つ
- 適度な運動を行う(太極拳やヨガなどがおすすめ)
- 十分な睡眠をとる
- ストレス管理を心がける(瞑想や深呼吸法など)
簡単な経絡マッサージと呼吸法
自身で身体に触れながら、時に呼吸に意識を向けながら「気」を整える方法もあります。
- 経絡マッサージ:
肺経(はいけい)のツボを軽くマッサージする
例:雲門(うんもん):鎖骨の下、肩の付け根あたり
尺沢(しゃくたく):肘の内側のしわ - 腹式呼吸法:
①リラックスした状態で座るか横になる
②鼻から息を吸いながら、おなかを膨らませる
③口からゆっくりと息を吐きながら、おなかをへこませる
④これを1日数回、5〜10分程度行う
これらの方法は、「気」の流れを整え、呼吸を楽にする効果が期待できます。

西洋医学との併用と注意点
東洋医学は、西洋医学と併用することで、より効果的な治療が期待できます。しかし、以下の点に注意が必要です:
- 漢方薬と西洋薬の相互作用:
一部の漢方薬は西洋薬の効果に影響を与える可能性があります。
必ず医師や薬剤師に相談しましょう。 - 重篤な症状の見分け:
以下のような症状がある場合は、すぐに医療機関を受診してください。
- 急激な息切れ
- 安静時の強い息切れ
- 胸痛を伴う息切れ
- 意識障害を伴う息切れ
- 長期服用時の注意:
漢方薬も医薬品になります。
長期服用する場合は定期的に医師の診察を受けましょう。
まとめ
東洋医学は、息切れを体全体のバランスの乱れとして捉え、個々の体質や症状に合わせた治療を行います。西洋医学的な治療と併せて、東洋医学的なアプローチを取り入れることで、より包括的な息切れの管理が可能になります。
また、日常生活における食事や生活習慣の改善、簡単なセルフケアを心がけることで、息切れの予防や軽減に役立つ可能性もあります。ですが、症状が重い場合や急激な変化がある場合は、速やかに医療機関を受診することが大切です。息切れを単なる息切れという状態で見過ごさないように、日々の健康を守るために、自分の体の変化に敏感になり、早めの対策を心がけましょう。
東洋医学と西洋医学、それぞれの長所を生かした統合的なアプローチが、今後ますます重要になっていきます。自分の体調に合わせて、適切な方法を選択し、自身の健康に心を留めて生きていくことが、よりよい日々を過ごすための大切な指針なのかもしれません。
西漢方では、お客様の体調に合わせた漢方のご提案をしております。
「最近、ちょっと息切れが気になる」「なんとなく体がだるい」など、どんな小さなお悩みでも大丈夫です。ひとりで悩むことなく、ぜひご相談ください。
大切な心と身体を整えてまいりましょう。
この記事を書いた人

西漢方薬店 漢方処方アドバイザー
西 智彦
鍼灸師、マッサージ師の国家資格と医薬品登録販売者の資格を持つ。
臨床歴20年の経験を活かし、子供からご高齢の方々の幅広い世代のお悩み、病気の改善のお手伝いをさせていただきます。
どうぞお一人で悩まずに、気軽にご相談ください。