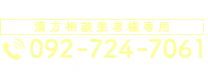漢方コラム
春から初夏へ、気と身体のバランスを整える

ぽかぽかとした春の陽気から、だんだんと汗ばむ初夏へと移り変わるこの季節。
自然界が活気に満ちていく一方で、「なんとなく体調がすぐれない」「気分が安定しない」と感じる方も多いのではないでしょうか。
特に40代以降になると、季節の変わり目に体がうまく馴染めず、自律神経の乱れや疲れを感じやすくなってきます。年齢とともに「気の流れ」や「調整力」が少しずつ変わってくるのは自然なことです。
今回は、東洋医学の視点を交えながら、春から初夏にかけての体調変化の理由と、日々の生活で取り入れやすいセルフケアをご紹介します。心と身体のバランスを整え、健やかな季節の移ろいを楽しみましょう。
目次
春から初夏に体調を崩しやすい理由とは?
気温差がもたらす自律神経への負担
春は年間でも最も寒暖差が大きい季節です。たとえば、気象庁の2023年春のデータによると、3月〜5月の平均日較差(1日のうちの最高・最低気温の差)は約9.5℃とされており、日によっては15℃以上の気温差が生じることもあります。
このような急激な気温の変化は、体温調整を担う自律神経に大きな負担をかけ、交感神経と副交感神経のバランスが乱れやすくなります。その結果、倦怠感や肩こり、頭痛、不眠といった不定愁訴が現れやすくなります。
今年も4月に入ってからも寒い日が続いたり、急にあたたかくなったり、最近はなかなか季節感をつかめない方も多いのではないでしょうか?
気圧の変動が引き起こす「気象病」
さらに、春は気圧の変化が激しい季節でもあります。低気圧が頻繁に通過し、天候が安定しないことで、耳の奥にある内耳が気圧の変化を敏感に感知し、それが自律神経に影響を与えると考えられています。これにより、頭痛、めまい、吐き気、だるさなどの症状が起こることがあり、「気象病」や「天気痛」と呼ばれています。
日照時間の変化と体内リズムの乱れ
春から初夏にかけては、日照時間も大きく変化します。東京の場合、1月初旬では約10時間だった日照が、5月末には約14時間にも達します。
この日照の変化は、脳内のホルモン分泌、特にセロトニン(幸福ホルモン)やメララトニン(睡眠ホルモン)のリズムを大きく揺さぶります。すると、睡眠の質が下がったり、気分が落ち込みやすくなるなど、心身への影響が出やすくなります。
日照時間の一覧がこちらで見れます。(国土交通省データー)
環境変化によるストレスの増加
春は進学や就職、異動、引っ越しなど「生活の節目」が重なる季節です。
厚生労働省が実施した「労働者のメンタルヘルスに関する調査」では、ストレスの要因として「職場や生活環境の変化」が上位に挙げられています。このような変化によるストレスは、自律神経を刺激し、心身のバランスを崩しやすくします。
(労働者のメンタルヘルスに関する調査)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r04-46-50_gaikyo.pdf
東洋医学の視点で見る春~初夏の不調
東洋医学では、季節ごとに身体が受ける影響を「五行説」で説明します。
春は「肝」、初夏は「心」がそれぞれ関係する臓腑とされ、それぞれが乱れることで身体の不調が起きやすくなると考えられています。
春は「肝」の季節
「肝」は気の巡りを司り、情緒や筋肉、目の働きなどに関係します。春に肝のエネルギーが過剰になると、イライラ、不安感、肩や首のこり、目の疲れなどが現れやすくなります。
初夏は「心」の季節
「心」は血流と精神状態に影響を与えるとされ、動悸、不眠、焦燥感、口内炎などの症状が出やすくなります。
これらの臓腑が過剰に働いたり、逆にエネルギーが不足することで、気(エネルギー)、血(栄養)、水(体液)のバランスが崩れ、体調不良が起きやすくなるのです。
季節の変わり目に実践したいセルフケア
食生活のポイント
- 肝を助ける「酸味」:酢の物、梅干し、柑橘類など。気の巡りを整える作用があり、春に起こりやすいイライラ感の軽減に役立ちます。
- 心を守る「苦味」:ゴーヤ、セロリ、緑茶など。体内の熱を冷まし、心の働きを安定させます。
- 水分補給:冷たい飲み物を控え、白湯や常温の水で体内を冷やしすぎないことが大切です。
生活習慣の整え方
- 朝の散歩やストレッチ:朝日を浴びながら身体を動かすことで、セロトニンの分泌が促され、体内時計がリセットされます。
- 深呼吸や瞑想の習慣:交感神経優位になりがちな春の時期には、意識的な呼吸や瞑想によって副交感神経を活性化させましょう。
- ぬるめのお風呂:38〜40℃のお湯にゆっくり浸かることで、血流が促進され、気の巡りが整います。
睡眠の質を高める
厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド(2023年改訂版)」によると、睡眠に不満を持つ人はそうでない人に比べ、体調不良のリスクが2倍以上に高まるとされています。
スマートフォンの使用は寝る1時間前までに控え、ブルーライトの刺激を避けるなど、睡眠環境を整える工夫も大切です。
年齢とともに低下する“調整力”をどう補う?
40代以降になると、季節の変化に対する身体の「順応力」が徐々に低下してきます。これは東洋医学でいう「気虚」「血虚」「陰虚」などの体質の変化によるものです。
- 気虚:疲れやすく、風邪をひきやすい
- 血虚:肌の乾燥、目の疲れ、貧血傾向
- 陰虚:のぼせ、不眠、乾きなどの症状が出やすい
これらは「年だから仕方ない」と諦めるのではなく、「身体が変化していることに気づく」ことが重要です。日々の生活の中で“整える習慣”を意識することで、大きな不調を防ぐことができます。
初夏におすすめのセルフケア習慣
春の不安定な気候を過ぎ、日差しが強まり始める初夏は、身体に熱がこもりやすく、食欲不振や倦怠感、むくみといった症状が出やすくなる季節です。この時期ならではの体調変化に備えて、以下のようなセルフケアを日常に取り入れてみましょう。
「汗」を上手にかく習慣をつける
発汗は体温を調整する大切な機能です。冷房のきいた室内で長時間過ごすことが増えると、発汗のリズムが乱れがちになります。朝の軽いウォーキング、ヨガ、ストレッチなどで無理のない発汗を促すことで、体内の熱や湿気を自然に排出できるようになります。汗をかいた後は、こまめに水分補給を行い、衣服の調整やシャワーで肌を清潔に保つことも忘れずに。
胃腸をいたわる「控えめ」な食事
初夏は気温の上昇とともに、胃腸の働きが弱りやすくなります。脂っこい料理や冷たい飲み物を摂りすぎると、消化に負担がかかり、食欲不振や胃もたれの原因になることも。冷やしすぎに注意しながら、きゅうり、トマト、豆腐など季節の野菜や消化の良い食材を中心に、バランスの取れた食事を心がけましょう。食欲がない日は、おかゆや温かいスープで胃腸を休ませるのもおすすめです。
「朝活」で自律神経のリズムを整える
日が長くなり、朝の時間が明るくなる初夏は「朝活」の始めどきです。起床後にカーテンを開けて朝日を浴び、軽い運動や深呼吸を取り入れるだけでも、セロトニンの分泌が促され、心身がシャキッと整います。こうした朝のルーティンは自律神経の切り替えにも効果があり、夜の眠りの質も高めてくれます。
まとめ
春から初夏にかけては、気温、気圧、日照時間、社会的環境、すべてが大きく変化する「ゆらぎの季節」です。
そんな時期に体調を崩しやすいのは、決してあなたのせいではありません。身体が自然に反応している証なのです。
だからこそ、自分の状態に敏感になり、「ちょっと疲れてるかも」「今日は休もうかな」と思ったときは、無理をせずに立ち止まる勇気も大切です。
小さなケアの積み重ねが、春を心地よく、そして健やかに過ごすための土台になります。季節の移ろいに寄り添いながら、あなた自身のペースで“整える”暮らしをはじめてみませんか?
この記事を書いた人

西漢方薬店 漢方処方アドバイザー
西 智彦
鍼灸師、マッサージ師の国家資格と医薬品登録販売者の資格を持つ。
臨床歴20年の経験を活かし、子供からご高齢の方々の幅広い世代のお悩み、病気の改善のお手伝いをさせていただきます。
どうぞお一人で悩まずに、気軽にご相談ください。