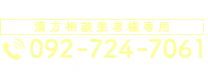漢方コラム
湿気に負けない体づくり

目次
梅雨時期の不調、その原因は「湿邪」かもしれません
梅雨の時期になると、なんとなく体がだるい、食欲がない、むくみやすい、気分が落ち込むなどの不調を感じる方が多くなります。これらの症状は、東洋医学で「湿邪(しつじゃ)」と呼ばれる、過剰な湿気が体に影響を及ぼすことが原因とされています。
「湿邪」は、体内の水分代謝を滞らせ、消化機能を弱め、気の巡りを阻害することで、さまざまな不調を引き起こします。特に女性は、ホルモンバランスの変化や冷えに敏感なため、湿邪の影響を受けやすいとされています。
今回の記事では、湿邪の特徴や症状、そして日常生活でできる対策についてお話をしていきたいと思います。梅雨を快適に過ごすためのヒントとして、ぜひ参考にしてください。
湿邪とは何か? 〜東洋医学から見る“湿気”の正体〜
東洋医学では、自然界の気候変化が人体に影響を与えると考えられており、特に「六邪(りくじゃ)」と呼ばれる外的要因の一つに「湿邪」があります。湿邪は、過剰な湿気が体内に侵入し、気血水の巡りを妨げることで、さまざまな不調を引き起こすとされています。
湿邪の特徴
- 重くて粘り気がある性質:体の巡りを悪くし、「体がだるい」「動きたくない」と感じるようになります。慢性的な疲労感やむくみが続くケースも少なくありません。
- 下に溜まりやすい:脚のだるさ、下半身のむくみ、関節の重さとして現れることがあります。雨の日に「関節が痛む」「足が重い」と感じる方は、この湿邪の影響を受けている可能性があると言われています。
- 脾(消化器系)に影響:「胃もたれ」「食欲不振」「下痢」「お腹の張り」などの症状が出やすくなります。冷たい飲み物が美味しくなる季節ではありますが要注意です!
- 気の巡りを阻害:体の巡りが悪くなると、「気」も停滞しやすくなります。気の巡りが滞ると、気分が落ち込んだり、頭がぼんやりしたり、集中力が続かないといった、精神的な不調が表れることがあります。
生活の中でいつの間にか、環境の影響を受けている時もありますよね。
簡単なチェックリストがありますので、ご自身の体調をチェックしてみてください。
こんな不調、湿邪が原因かも? チェックリスト
以下のような症状がある方は、湿邪の影響を受けている可能性があります。
- 朝起きても疲れがとれない
- 手足が重だるく感じる
- お腹が張って食欲がない
- お通じがゆるくなる
- 頭がぼんやりして集中力が落ちる
- 関節がこわばる、重い
- 気分が落ち込みやすい
- 肌の調子が悪く、湿疹が出やすい
一つでも当てはまる場合は、対策を取り入れて少しでも状態を和らげてみませんか?
今日からできる湿邪対策!生活習慣・食事・セルフケア
■ 食事で湿を追い出す
湿邪を体外に排出するためには、利水作用や発汗作用のある食材を積極的に摂取することが効果的です。
利水作用のある食材
- ハトムギ:利尿作用があり、むくみの改善に効果的です。
- 小豆:体内の余分な水分を排出し、消化機能を助けます。
- 冬瓜:利尿作用が強く、体内の湿を取り除きます。
- とうもろこし:利尿作用があり、胃腸の働きを助けます。
- きゅうり:カリウムを多く含み、体内の余分な水分を排出します。
発汗作用のある食材
- 生姜:体を温め、発汗を促します。
- ネギ:体を温め、気の巡りを良くします。
- シソ:発汗を促し、気の巡りを助けます。
- 唐辛子:発汗作用があり、体を温めます。
これらの食材を使ったスープや煮物など、温かい料理を摂ることで、湿邪の排出を促すことができます。
■身体を温めて巡りを良くする
湿邪は冷えとともに体内に入り込みやすくなります。
以下の方法で体を温め、気血水の巡りを良くしましょう。
- 湯船につかる:38〜40℃のぬるめのお湯に10〜15分程度浸かることで、体を芯から温めます。
- 足湯をする:足元を温めることで、全身の血行を促進します。
- 温かい飲み物を摂る:白湯や生姜湯など、体を温める飲み物を選びましょう。
- 軽いストレッチやヨガ:血流を促し、気の巡りを良くします。
■ 室内環境を整える
湿邪の影響を最小限に抑えるためには、住環境の湿度管理が重要です。
- 除湿器やエアコンのドライ機能を活用:室内の湿度を40〜60%に保つよう心がけましょう。
- 定期的な換気:1日2〜3回、10分程度の換気を行い、湿気を外に逃がします。
- 寝具や衣類の管理:通気性の良い素材を選び、こまめに干すことで湿気を防ぎます。
- 除湿剤の活用:クローゼットや靴箱など、湿気がこもりやすい場所に設置しましょう。
湿邪に強い「脾(ひ)」を育てる
東洋医学では、「脾(ひ)」という臓器が湿邪と深く関わっていると考えられています。脾は西洋医学の「胃腸」に近い働きを持ち、食べたものをエネルギーに変えて体中に送る役割を担っています。湿邪はこの脾の働きを弱め、消化力や代謝を低下させるため、結果として体内に湿がたまりやすくなるのです。
脾を元気に保つためには、以下の習慣が効果的です。
- 朝食をしっかり食べる
朝は一日の中で脾の働きが最も活発になる時間帯。温かいスープやおかゆなど、消化の良いものを摂るとエネルギーがしっかり巡ります。 - よく噛んで食べる
消化は口から始まります。ひと口30回を目安にゆっくり噛むことで、脾への負担を減らすことができます。 - 冷たいものを控える
冷たい飲食物は脾の働きを冷やし、湿邪をためやすくします。夏でもなるべく常温や温かいものを選びましょう。
日々のちょっとした工夫で脾を守ることは、湿邪に負けない体づくりに直結します。体の内側から健やかさを育てる意識を、ぜひ取り入れてみてください。
心のケアも忘れずに|湿邪とメンタルの関係
湿邪は体だけでなく、心にも影響を及ぼします。気分の落ち込みやイライラ、不安感などを感じることが増える場合は、以下の方法で心のケアを行いましょう。
- 規則正しい生活リズムを整える:十分な睡眠とバランスの取れた食事を心がけましょう。
- リラックスできる時間を持つ:アロマテラピーや音楽、読書など、自分に合ったリラックス法を見つけましょう。
- 深呼吸や瞑想を取り入れる:呼吸を整えることで、自律神経のバランスを保ちます。
- 無理をせず、自分をいたわる:疲れを感じたら、無理をせず休息を取ることが大切です。
自分の体と心の声を聞く習慣を
梅雨や夏の湿気が多い季節は、私たちの体と心に静かに負担をかけてきます。
日々の忙しさに追われていると、その変化に気づかないこともありますが、「ちょっといつもと違うな」と感じたときこそ、自分の内側と向き合うチャンスでもあります。
湿邪は目に見えない存在ですが、体のだるさや消化不良、気分の落ち込みなど、確かなサインを通じて私たちに影響を及ぼしています。逆に言えば、そうしたサインに耳を傾け、日常の中で小さなケアを重ねることで、梅雨を快適に過ごすことができるのです。
食事、生活習慣、心の在り方…
これらを少し意識するだけで、体は驚くほど軽やかになります。今日からできる湿度への対応、湿邪対策を、無理なく生活に取り入れながら、季節に負けない、しなやかな心身を育てていきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
ぜひお困りの際にはわたしたち西漢方薬店にご相談くださいませ!
心と体が整うことで、毎日の暮らしがより豊かになることを願っています。
この記事を書いた人

西漢方薬店 漢方処方アドバイザー
西 智彦
鍼灸師、マッサージ師の国家資格と医薬品登録販売者の資格を持つ。
臨床歴20年の経験を活かし、子供からご高齢の方々の幅広い世代のお悩み、病気の改善のお手伝いをさせていただきます。
どうぞお一人で悩まずに、気軽にご相談ください。