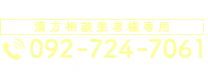お知らせ
漢方偉人伝 医緩(いかん)
「西漢方薬店 漢方チャンネル」に「漢方偉人伝 医緩(いかん)」を公開しました!
病膏肓に入る ― 名医・医緩と景公の逸話に見る東洋医学の奥深さ
古代中国に伝わる医学の物語には、今日にも通じる知恵が数多く詰まっています。
そのひとつが、「病膏肓(こうこう)に入る」という言葉の由来にもなった、**景公と名医・医緩(いかん)**の逸話です。

名医・医緩と奇妙な夢の予兆
ある日、古代中国の君主・景公が重い病に倒れました。
その知らせを受け、秦の国から名医・医緩が派遣されることになります。
医緩が到着する前夜、景公は不思議な夢を見ました。
そこには二人の子どもが現れ、「この病は名医でも治せない」と話していたのです。
子どもたちは「この病は**膏肓(こうこう)**にある」とも言っていたといいます。
的中する診断 ― 膏肓という難所
実際に医緩が景公を診察すると、まさに夢で見た通りの診断を下しました。
彼はこう言いました:
「この病は膏肓にあります。薬も届かず、鍼を打つこともできません。」
「膏肓」とは、肩甲骨の内側・肺の奥に近い部位にある経穴で、
現代でいうと背部の要穴のひとつとされる重要なポイントです。
この部位は鍼を刺すにも肺を傷つける恐れがあり、当時は治療不可能な領域とされていたのです。
「病膏肓に入る」の語源とその意味
この出来事から生まれた言葉が、現在でも使われている慣用句、
「薬石効なく、病膏肓に入る」
です。
ここでの「薬」は漢方薬を、「石」は**石針(=鍼)**を指します。
つまりこの言葉は、「薬も鍼も効かないほど重い病が身体の奥深くに入り込んだ」
=もはや治療が困難な状態を表現しているのです。
現代でも、「膏肓に入る」という表現は、不治の病や手遅れな状態を象徴する言葉として用いられています。
東洋医学の知恵と限界を知ることの大切さ
この逸話は、名医の診断力のすばらしさと同時に、いかに東洋医学が体の深層を重視してきたかを物語っています。
また、治療の限界を正直に伝える誠実さと、病と向き合う姿勢の大切さも教えてくれます。
【西漢方薬店より】オンライン漢方相談のご案内
西漢方薬店では、オンラインによる漢方相談を承っております。
現代の疾患においても、「どこに原因があるのか」を見極めることが非常に重要です。
「症状が長引いている」「原因がよくわからない」という方は、
ぜひ一度、漢方専門家による体質診断と処方相談をご利用ください。
東洋医学の視点から、あなたに合った解決策を一緒に見つけてまいります。
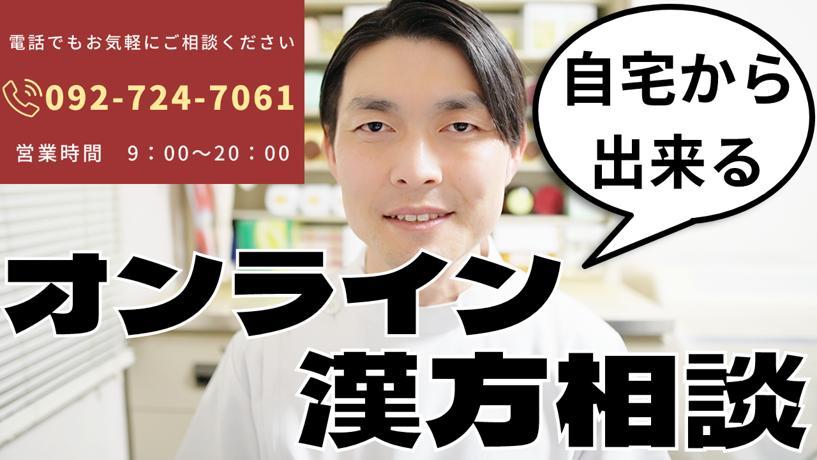
この記事を書いた人

西漢方薬店 漢方処方アドバイザー
西 智彦(臨床歴20年)
鍼灸師、マッサージ師の国家資格と医薬品登録販売者の資格を持ち、学術発表症例発表実績として第24回経絡治療学会学術大会東京大会『肝虚寒証の症例腰痛症』等、また伝統漢方研究会会員論文集の学術論文からメディア取材まで幅広い実績もあります。
どうぞお一人で悩まずに、気軽にご相談ください。