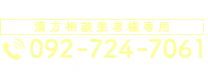お知らせ
漢方偉人伝 扁鵲(へんじゃく)
「西漢方薬店 漢方チャンネル」に「漢方偉人伝 扁鵲(へんじゃく)」を公開しました!
扁鵲 ― 脈診を確立した中国医学の始祖
古代中国・春秋戦国時代に登場した伝説的な名医、扁鵲(へんじゃく)。
彼は中国医学の祖として、数多くの診断技術と治療法を後世に伝えました。
その名は、**インドの名医・耆婆(ぎば)**と並び称され、後の東アジアでは「扁鵲=名医」を意味する代名詞としても使われるようになりました。

脈診の理論を確立した扁鵲の功績
扁鵲の最大の功績は、脈診(みゃくしん)に関する理論の確立です。
中国の歴史書『史記』には、
「脈を診て病を知る者は、すべて扁鵲の流れをくむ」
と記されており、彼の脈診理論がいかに大きな影響を与えたかがわかります。
脈診とは、手首に触れて脈の状態から内臓の働きや気血の巡り、病の性質や深さを読み取る診断法であり、現在の漢方医学・鍼灸にも欠かせない技術です。
有名な逸話:趙鞅を救った予言の診察
扁鵲にまつわる数々の逸話の中でも、特に有名なのが紀元前501年の「趙鞅(ちょうおう)」の診察です。
病に倒れ、昏睡状態に陥った趙鞅を診た扁鵲はこう断言しました:
「この病は深くない。三日以内に意識を取り戻すだろう。」
そして予言通り、趙鞅は3日後に回復。
この診断力は、当時の人々にとって神業のように映ったことでしょう。
活動期間300年? 一人ではなく流派の象徴か
扁鵲の活動記録は広範囲かつ長期間にわたり、実に300年近くにわたるという説もあります。
このため、「扁鵲」は個人の名前ではなく、一つの医学派の総称ではないかという見方も存在します。
しかし、2010年代に発掘された老官山漢墓の竹簡資料により、扁鵲が実在の人物であった可能性が高まったことも報告されています。
現代まで続く影響力
扁鵲は、現代の東洋医学にもつながる以下のような技術の原型を築きました:
- 脈診・望診・問診・切診による四診法
- 鍼灸や経絡を使った治療法
- 病の深さを見極める診断理論
このように、彼の功績は数千年を経ても色褪せることのない医学の原点として、いまなお尊敬されています。
【西漢方薬店より】オンライン漢方相談のご案内
西漢方薬店では、オンラインでの漢方相談を受け付けております。
扁鵲が重視したように、体の状態を丁寧に見極めることが漢方の第一歩です。
「どの薬が合うのか分からない」「体質や症状に合った処方を知りたい」
そんな方は、ぜひ専門家にご相談ください。
あなたの気・血・水のバランスを見極めた処方をご提案いたします。
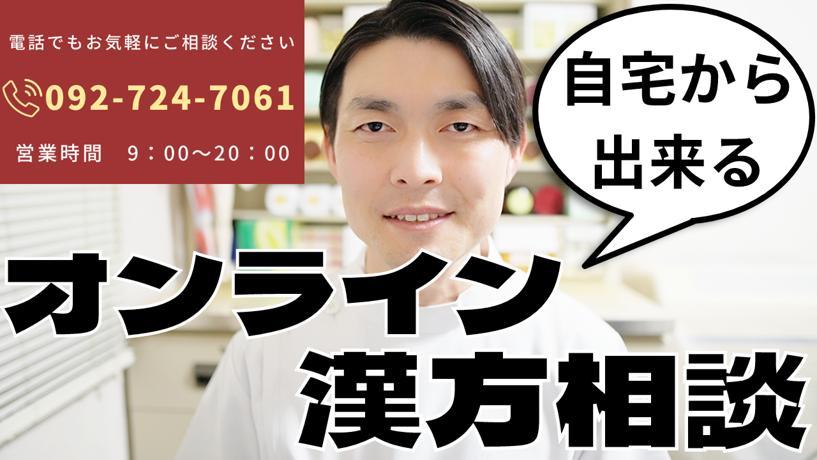
この記事を書いた人

西漢方薬店 漢方処方アドバイザー
西 智彦(臨床歴20年)
鍼灸師、マッサージ師の国家資格と医薬品登録販売者の資格を持ち、学術発表症例発表実績として第24回経絡治療学会学術大会東京大会『肝虚寒証の症例腰痛症』等、また伝統漢方研究会会員論文集の学術論文からメディア取材まで幅広い実績もあります。
どうぞお一人で悩まずに、気軽にご相談ください。