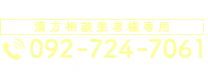お知らせ
漢方偉人伝 董汲(とうきゅう)
宋代に脚気治療の礎を築いた董汲の功績と現代漢方への影響
儒学と医学を融合した北宋の名医・董汲
宋代の医療に革新をもたらした医師・**董汲(とうきゅう)**は、儒学と医学の素養を併せ持つ「儒医」として知られています。
彼は北宋の崇寧・大観年間に活躍し、**1093年に中国初の個人医学叢書『董汲医学論著三種』**を著しました。
この書は以下の三部から構成されています:
- 『脚気治法総要』
- 『小児斑疹備急方論』
- 『旅舍備要方』
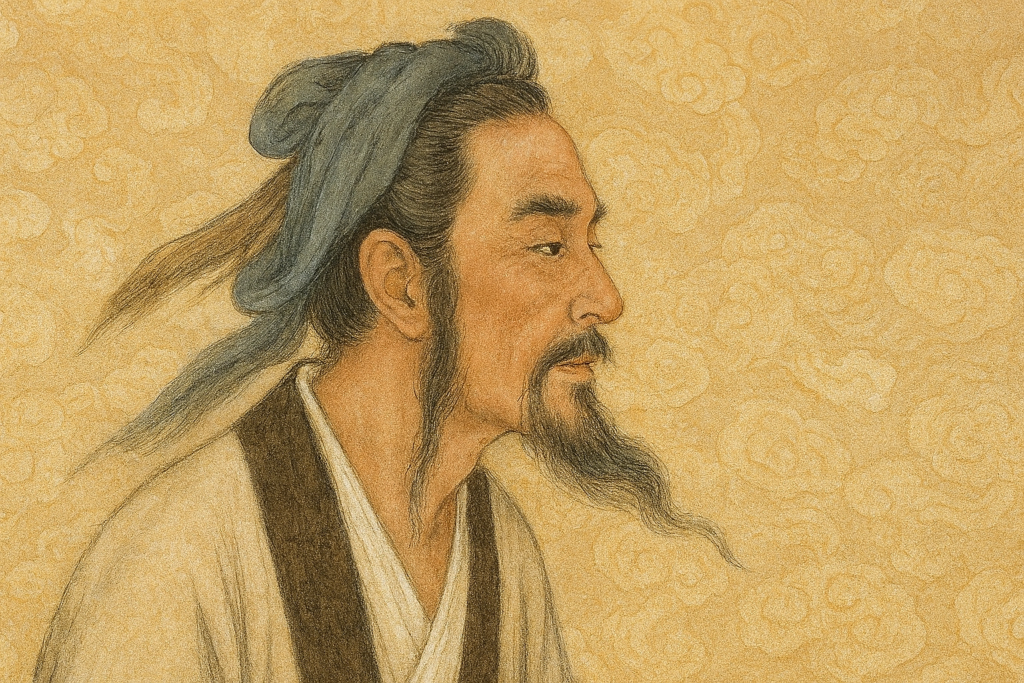
脚気病に対する画期的な漢方理論
当時、致死的な疾患とされた脚気病に対して、董汲は独自の理論を打ち立てました。
彼はその原因を「湿邪が冷熱を兼ねる」とし、気候や地理条件に応じた治療法を確立。
症状の進行度に応じて46種の処方を用意し、治療を体系化した点が特筆されます。
この考え方は、現代においても「湿邪」と「寒熱」のバランスを重視する漢方治療の基本的枠組みに通じています。
小児医学への貢献──独立した診療領域の確立
『小児斑疹備急方論』では、斑疹(発疹性疾患)に関する研究を通じて、
小児医学を内科から分離・独立させる基礎を築きました。
特に有名な治療原則:
「急驚には冷泻を用い、慢驚には温補を用いる」
この言葉は、急性のけいれんには熱を冷ます治療を、慢性のけいれんには体力を補う治療を行うという、
当時としては非常に先進的な概念を示しています。
旅先の応急処置にまで及ぶ医学の実用化
さらに『旅舍備要方』では、旅先での緊急時対応を重視し、
外傷や食中毒への応急処置法を記録しました。
彼は小麦粉に含まれる毒性の可能性にも触れており、当時の食生活に警鐘を鳴らす形での指摘は、
今でいう食品衛生の先駆けともいえる内容です。
董汲の視点は、現代漢方の根本に通じている
董汲が示した「症状の進行度に応じた処方の使い分け」や「体質・環境・病態の三位一体の考え方」は、
現代の東洋医学においても極めて重要な原則とされています。
ご自身の体調には、体質に合った処方を
漢方薬は、一人ひとりの体質や生活環境に応じて最適な処方が異なります。
宋代の名医・董汲のように、全体像を丁寧に把握したうえでの処方選びが肝心です。
西漢方薬店ではオンラインでの漢方相談を行っております。
どのような症状でも、お気軽にご相談ください。
あなたに合った最善の処方をご提案いたします。
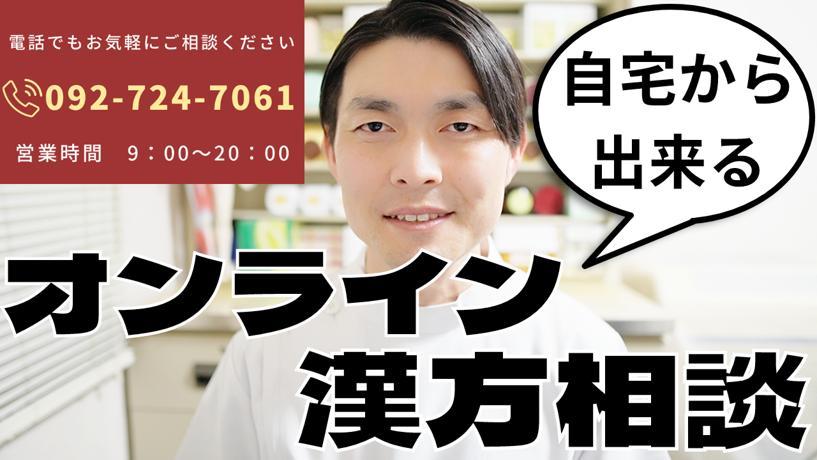
この記事を書いた人

西漢方薬店 漢方処方アドバイザー
西 智彦(臨床歴20年)
鍼灸師、マッサージ師の国家資格と医薬品登録販売者の資格を持ち、学術発表症例発表実績として第24回経絡治療学会学術大会東京大会『肝虚寒証の症例腰痛症』等、また伝統漢方研究会会員論文集の学術論文からメディア取材まで幅広い実績もあります。
どうぞお一人で悩まずに、気軽にご相談ください。